【読書】はなとゆめ/冲方丁 枕草子ではなく、清少納言本人の物語
冲方丁が描く清少納言の物語
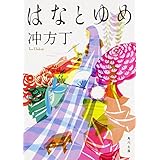 |
新品価格 |
だが、それを書いた本人である清少納言についてどの程度知っているか。
文書を書いた人間の背景がわかってこそ、その本質を理解できる。
どのような政治的背景、人間関係、精神状態において記していたのか。
作者に焦点を当てて描く本作で、清少納言という人間が形を帯びる。
定子を尊敬する、敬愛する清少納言、むしろ愛するといっても過言ではない。
定子という人間と彼女を愛する清少納言、二人が直面する様々な問題の中で繋がりがより深まる。
太陽は落日こそが美しい
最後まで定子に使え、敬愛してその思いを込めた枕草子。
この言葉もまた、定子に捧げた言葉であろう。
現代では感じることのできない感覚
「朝廷は、愛のせいで人が死ぬ場所であるのですから」
朝廷という場所がどのような場所か、我々現代人にはイメージしづらい。
だが、この一文がすべてだと感じる。
彼女は誰を愛し、誰に愛されたのか。
心のそこから仕える人間を得る
「この一瞬が千年でも続いて欲しい」
もともと人付き合いがあまり得意でなかった清少納言は、彼女によって徐々に変化していく。
定子の幸せが自分の幸せと化していく。
そこまでの熱烈な思いが枕草子にこもっている。
硬くて脆い、それが政治
「政治のように硬く鋭い、その代わりにいつ自他もろともに砕け散るかわからぬ」
政治に対する表現が非常に興味深い。
政治は、柔らかくあってはならない。
すべてが合理的な理由のもとになされる。
その結果、自分が砕けてしまうことももちろん想定される。
温情などない、そんな世界。
不自由な暮らしの中で、紙の上で自由を得た
「紙の上では、わたしは自由でした」
自分自身は和歌が特別得意ではなく、父親が和歌の達人であったからこそプレッシャーを感じている。
だが、好き勝手に書いたものを定子は読みたいと。
離れていても書くことで、それを定子が読むことで、そばに仕えている、そう思えることが幸せだった。
清少納言は紙の上で自由になった。
勝手に感じていたプレッシャーから解き放たれ、敬愛する人のために筆を取る。
「みな人の花や蝶やといそぐ日も わが心をば君ぞ知りける」
関連記事
aichikenmin-aichi.hatenablog.com
aichikenmin-aichi.hatenablog.com
aichikenmin-aichi.hatenablog.com